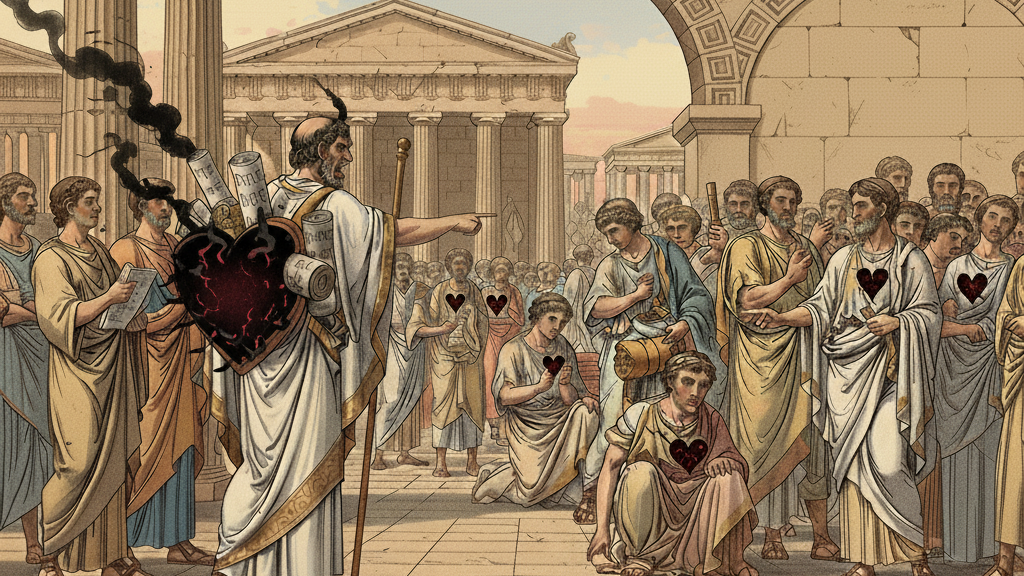“Ad ista concitari insania est.”
「そのようなことで心を乱されるのは、狂気の沙汰である」
—— Seneca, De Ira, 2.25.1
【解説】
些細なことでカッとなるのは、賢者のすることか、それとも狂人のすることか。セネカは、日常の些事に対する怒りの反応を「狂気」と断じ、厳しく戒めます。召使いの動きが鈍い、飲み物の水がぬるい、寝床が乱れているといった、取るに足らない出来事にいちいち腹を立てるのは、理性を失った状態に他ならないというのです。この痛烈な指摘は、私たちの感情がいかに些細なきっかけで燃え上がりうるかを浮き彫りにします。セネカによれば、真の強さとは、外的状況に揺さぶられない不動の魂を持つことであり、つまらないことで怒るのは魂の弱さの証左に他ならないのです。
“Maximum remedium irae dilatio est”
「怒りに対する最大の治療法は、引き延ばすことである」
—— Seneca, De Ira, 3.12.4
【解説】
燃え盛る炎を消すには、水をかけるよりまず時間を置くべきでしょうか。セネカは、怒りという激しい情念に対する最も効果的な対処法として「時間」という処方箋を提示します。怒りの最初の衝動は激しく、理性の目を曇らせてしまいますが、少し時間を置くことでその熱は冷め、心を覆っていた暗雲も晴れていくというのです。彼は、判断を急がず、一日、いや一時間でも待つことで、衝動的な反応が冷静な判断へと変わる可能性を説きました。この「引き延ばし」という自制の技術は、感情の波にすぐに飲み込まれるのではなく、距離を置いてそれを客観視するための、時代を超えた知恵と言えるでしょう。
“Dat poenas dum exigit.”
「(怒りは)罰を要求しながら、罰を受ける」
—— Seneca, De Ira, 3.5.6
【解説】
他者を傷つける刃は、同時に自らの手をも傷つけるのでしょうか。セネカは、怒りという感情が持つ自己破壊的な性質を、この鋭い対句で見事に表現しました。怒りは他者への報復や罰を求めますが、その過程で怒っている本人自身が安らぎを失い、憎しみに心を蝕まれ、人間関係を破壊するという「罰」を受けることになるのです。この言葉は、怒りが他者に向かう攻撃であると同時に、自分自身の魂に向けられた攻撃でもあることを示唆しています。怒りを発散させることは、一見すると力の行使のように見えますが、実際には自らを害する行為に他ならないという、ストア派の深い洞察がここに凝縮されています。
“Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.”
「他人の欠点は我々の目の前にあり、我々自身の欠点は背中にある」
—— Seneca, De Ira, 2.28.7
【解説】
私たちは鏡がなければ自分の顔を見られないように、他者の助けなしに自分の欠点を見ることは難しいのかもしれません。セネカはこの有名な格言で、人間が他人の過ちには敏感でありながら、自分自身の過ちにはいかに鈍感であるかを指摘します。私たちは他人の言動にすぐさま腹を立てますが、その前に自分も同じような過ちを犯していないかと省みることは稀です。この言葉は、怒りの感情が湧き上がったとき、その矛先を外に向ける前に、まず内なる自己へと向けるべきだと教えています。他者への不当な怒りを自制する鍵は、自分自身の不完全さを認める謙虚さの中にあると言えるでしょう。
“οἱ γὰρ ὀλίγων δεόμενοι πολλῶν οὐκ ἀποτυγχάνουσι.”
「なぜなら、わずかなものしか必要としない人々は、多くのものを失うことがないからだ」
—— Plutarch, On the Control of Anger, 461c
【解説】
持たざる者は、失う悲しみも知らないのでしょうか。プルタルコスは、怒りを自制するための心構えとして、欲望を減らすことの重要性をこの簡潔な一句で説きます。多くのものを求め、贅沢な生活に慣れてしまうと、少しでも期待が裏切られたり、思い通りにならなかったりするだけで、不満や怒りが生じやすくなります。しかし、もとから多くを求めず、質素な生活で満足できる人は、そもそも失望する機会が少ないのです。この言葉は、怒りの根源がしばしば満たされない欲望にあることを示唆しています。心の平穏を保つためには、外的なものを追い求めるのではなく、内的な満足、すなわち自足の精神を培うことが不可欠だという古代の知恵がここにあります。
“ἀόργητος μὲν γὰρ εὐθέως […] γενέσθαι τις οὐ δύναται, κατασχεῖν δὲ τὸ τοῦ πάθους ἄσχημον δύναται.”
「というのも、怒らぬ者にはすぐにはなれないが、その情念の醜さを抑えることはできるからだ」
—— Galen, De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 4
【解説】
完璧な聖人になることと、より善い人間になろうと努めること、どちらが現実的な目標でしょうか。医師でもあるガレノスは、魂の治療において現実的なアプローチを取ります。彼は、怒りという感情を完全になくすことは、望んですぐにできることではないと認めます。しかし、怒りの感情が湧き上がったとしても、その醜い表出、すなわち怒鳴ったり、暴力に訴えたりといった行動を抑制することは可能だと説くのです。これは、理想を追い求めるあまり挫折するのではなく、達成可能な目標から始めることの重要性を示唆しています。怒りの自制への道は、感情の完全な消去ではなく、その破壊的な行動を制御するという、着実な一歩から始まるのです。
“ὥσπερ κύων ὑπὸ νομέως, ὑπὸ τοῦ λόγου τοῦ παῤ αὐτῷ ἀνακληθεὶς πραϋνθῇ”
「あたかも犬が羊飼いによって呼び戻されて穏やかになるように、自分の中の理によって」
—— Galen, De placitis Hippocratis et Platonis, 5.7
【解説】
私たちの心の中には、忠実な番犬と、それを導く羊飼いがいるのでしょうか。ガレノスはプラトンの『国家』からこの鮮やかな比喩を引用し、魂の構造を説明します。プラトンによれば、魂の「気概(θυμός)」、すなわち怒りや闘争心といった部分は、それ自体は善でも悪でもなく、まるで番犬のような存在です。この犬が理性の声に耳を傾ける忠実な盟友となるとき、魂は秩序を保ちます。この一節は、怒りを根絶すべき悪と見なすのではなく、理性の指導のもとで正しく用いられるべき力として捉えるプラトンの思想を示しています。自制とは、この内なる番犬を、暴れさせるのではなく、賢明な主人の声に従うよう訓練することに他ならないのです。
“οὐ γὰρ ἀεὶ ἡ ὄρεξις καὶ ὁ λόγος συμφωνεῖ.”
「というのも、欲望と理性は常に一致するわけではないからだ」
—— Aristotle, Eudemian Ethics, 1224a
【解説】
私たちの心は、常に一つの方向を向いた調和のとれた合唱隊なのでしょうか、それとも時に不協和音を奏でる二人の奏者なのでしょうか。アリストテレスは、この簡潔な言葉で、人間の内なる葛藤の根源を明らかにします。魂の中には、快不快に従って何かを求める「欲望(ὄρεξις)」と、善悪や利害を判断する「理性(λόγος)」が存在しますが、この二つは必ずしも同じことを命じるとは限りません。怒りもまた欲望の一形態として、理性の判断に反して暴走することがあります。この一句は、自制という徳がなぜ必要とされるのか、その根本的な理由を示しています。それは、私たちの魂が、調和と対立の可能性を同時にはらんだ、複雑な構造を持っているからに他ならないのです。
“ὥσθʼ ὁ μὲν θυμὸς ἀκολουθεῖ τῷ λόγῳ πως, ἡ δʼ ἐπιθυμία οὔ.”
「したがって、怒りはどうにか理性に付き従うが、欲望はそうではない」
—— Aristotle, Nicomachean Ethics, 1149b
【解説】
悪徳にも、より矯正しやすいものと、そうでないものがあるのでしょうか。アリストテレスは、怒りの無自制と、肉体的な快楽への無自制を比較し、興味深い分析を示します。彼によれば、怒りは理性が「侮辱された」と判断したことに反応するため、ある意味で理性の声を聞いています。一方、快楽への欲望は、理性の判断を一切無視してただ快を求めるため、より動物的で矯正が難しいというのです。この言葉は、怒りが危険な情念であると同時に、理性の導きを受け入れる可能性を秘めていることを示唆しています。怒りの自制とは、この「どうにか付き従う」性質を利用し、理性の支配を完全に確立する試みであると言えるかもしれません。
(編集協力:中山 朋美、内海 継叶)
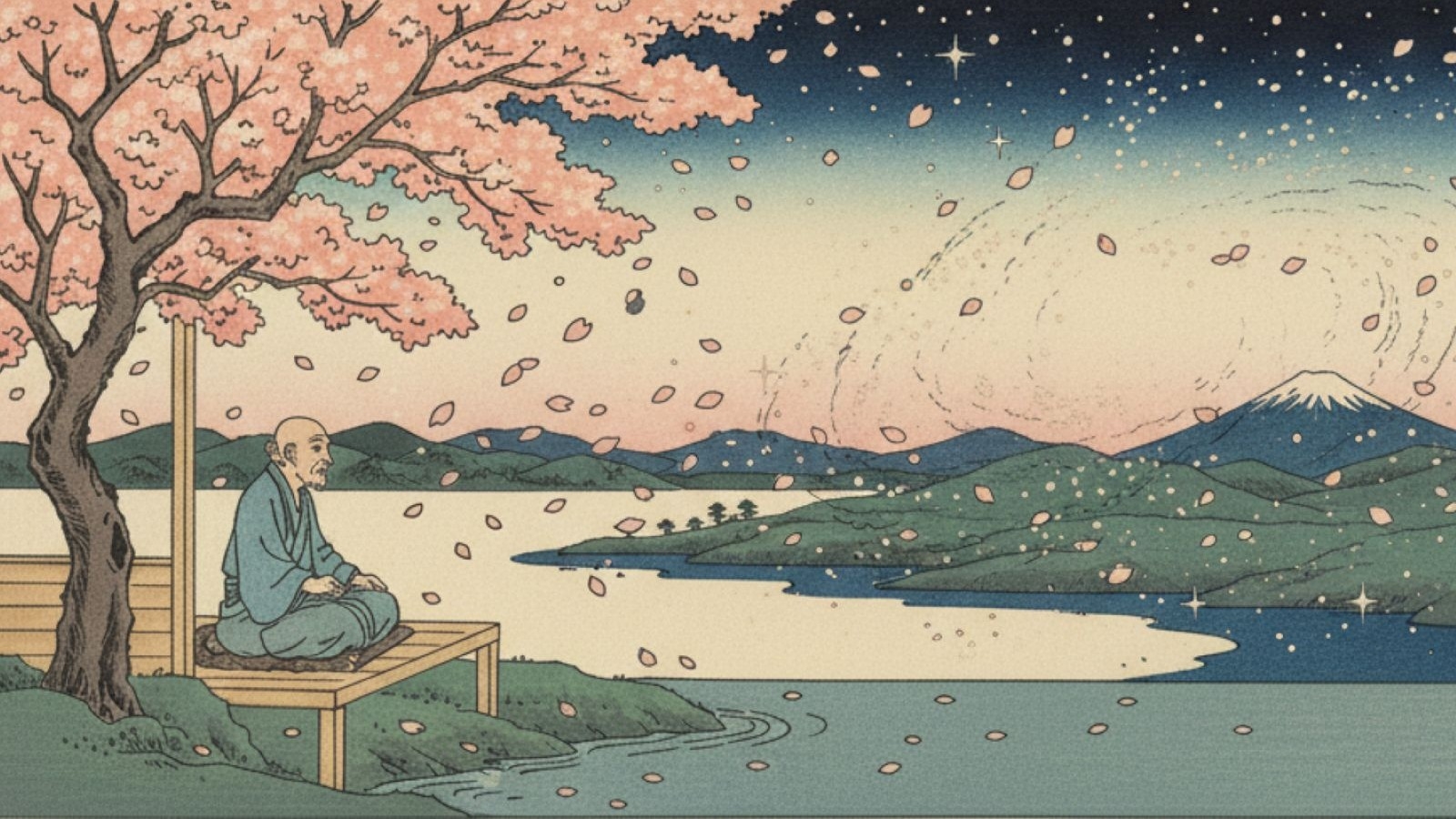
日本の季節観:文人たちのまなざし
日本の文人たちは、小説や随筆などの多様な表現形式を通して、移ろいゆく季節や生命の営みに深く向き合ってきました。彼らの繊細な感性と鋭い観察眼は、私たちに自然との対話の扉を開き、日常の風景の中に隠された美と哲学を教えてくれます。

日本の原風景:土地が語る記憶の物語
ハエの羽音に亡き人を重ね、一本足の案山子(かかし)に神様を見る。 日本人にとって不思議な物語は空想ではなく、すぐ隣にある「生活」そのものでした。 海の彼方への憧れや、古びた塚に残る伝説。柳田國男や小泉八雲らが拾い集めた、恐ろしくも優しい「心の原風景」を旅してみませんか。
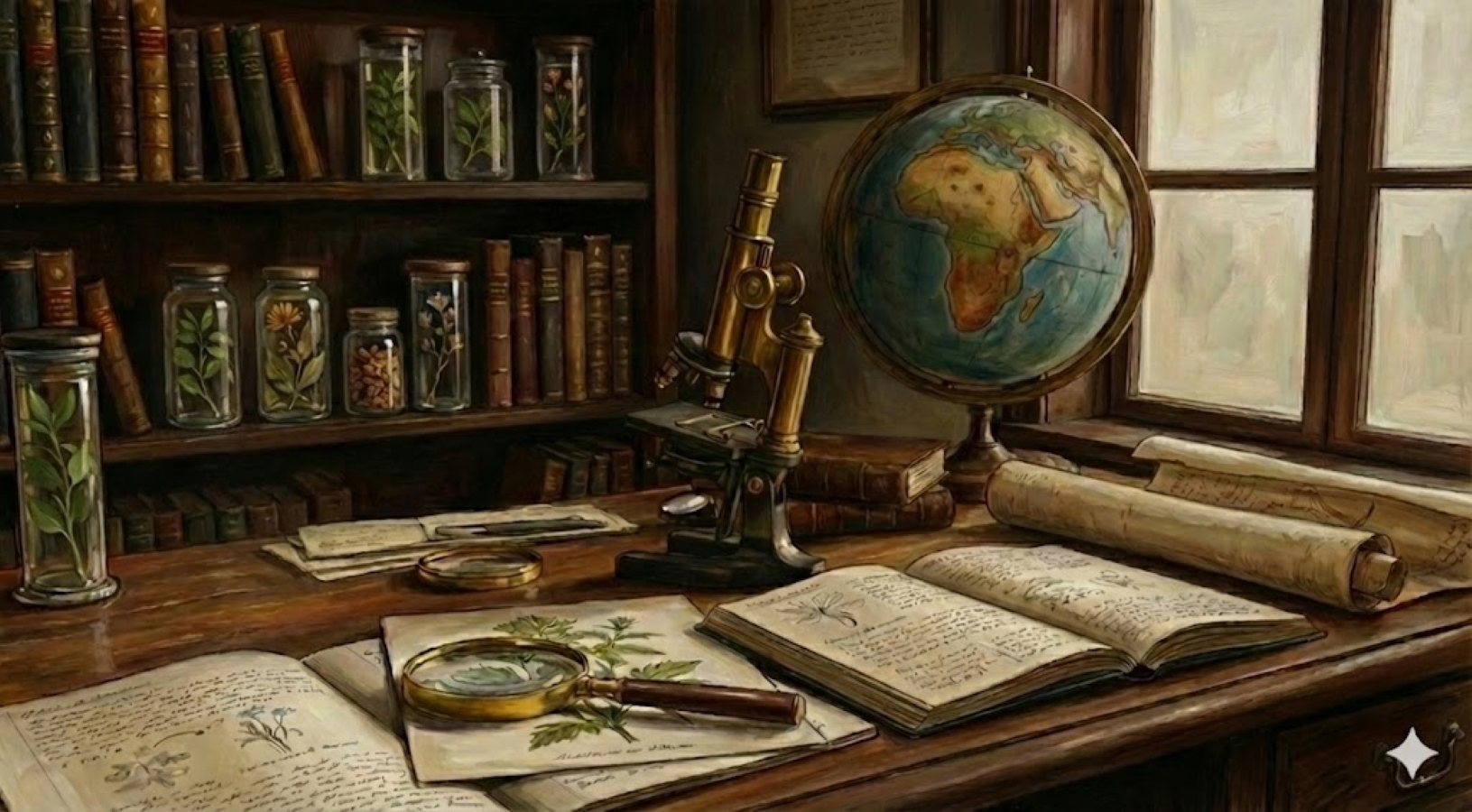
「理屈」を超えた驚異へ:科学者たちが覗いた美しき深淵
科学は、無機質な計算ではありません。それは人知を超えた自然への畏敬であり、終わりのない美の探求です。雪の結晶に宇宙を見、道端の草に命の猛々しさを感じる————。論理の果てにこそ現れる、圧倒的な「神秘」と対峙した知の冒険者たち。その静謐で熱い魂の記録に触れます。

「私」を叫ぶ魂:近代女性が描く、運命と矜持の物語
女性の人生は、運命への諦念で塗り固められるべきでしょうか。それとも、社会の壁を突き破り、自らの「生」を勝ち取るための戦いでしょうか。一葉が吐いた乾いた自嘲、晶子が愛する者のために放った痛烈な叫び。時代という鎖に抗い、泥にまみれながらも「私」を確立しようとした、彼女たちの魂の叫びに耳を澄ませます。