「運の悪い時には何事も思うように行かんもので」 —— 夏目 漱石『吾輩は猫である』
【解説】
人生は、いつも計画通りに進むとは限らないのではないでしょうか。この一文は、主人公である苦沙弥先生が、年に一度の楽しみである芝居見物を前に体調を崩してしまった際の嘆きの言葉です。妻を喜ばせようというささやかな計画も、突然の悪寒と眩暈によって脆くも崩れ去ろうとしています。そこには、自分の意志や努力だけではどうにもならない「運」というものの存在と、物事がままならない人生のはかなさに対する諦念が滲んでいます。このどうしようもない不運こそが、かえって有為転変の世を生きる人間の定めなのだと、漱石は滑稽な日常の一コマを通して静かに語りかけているように思われます。
「時間と云う分らぬものの流れに棹さして」 —— 夏目 漱石『文芸の哲学的基礎』
【解説】
人生を一つの船旅に喩えるなら、私たちは一体どんな海を漕いでいるのでしょうか。この詩的な一句は、漱石が自身の哲学や芸術観を語った講演録の中に登場します。彼は、人間という存在を、その正体も行き先も定かではない「時間」という巨大な流れの中を、ただ懸命に棹をさして進んでいく儚い旅人のように捉えました。自分の力ではどうにもならない大きな運命の流れの中で、それでもなお抗い、生きようとする人間の姿が目に浮かぶようです。この壮大で、どこか心もとないイメージは、人生の無常と、それに立ち向かう人間の意志の尊さを同時に感じさせ、私たちの思索を深く誘うはずです。
「ただ死と云う事だけが真だよ」 —— 夏目 漱石『虞美人草』 [甲野さん]
【解説】
この世に確かなものなど何もない、そう感じたことはありませんか。この一文は、厭世的な哲学者である甲野さんが、友人との会話の中でぽつりと漏らす言葉です。彼は、人間社会のあらゆる物事は夢のように不確かで移ろいやすいと考えています。その彼にとって、唯一確実なもの、疑いようのない真実として存在するのが「死」なのです。この冷徹な言葉は、人生のはかなさや物事の無常を突き詰めた先にある、究極のリアリティとしての死を喝破しています。このニヒリスティックとも取れる強い断言は、逆説的に、だからこそ「生きている今」という不確かな時間をどう過ごすのかを、読者に鋭く問いかけてくるようです。
「ただ淡い薫を残して消えた香のようなもので、ほとんどとりとめようのない事実である。」 —— 夏目 漱石『硝子戸の中』
【解説】
遠い過去の記憶とは、まるで淡い香りのように、掴もうとすると指の間からすり抜けてしまうものかもしれません。この美しい一文は、漱石が自身の幼少期を振り返り、早くに亡くした母の面影をたどる随筆の中にあります。母がどこで生まれ、どんな奉公をしていたかという話も、今となっては確かな手触りを失い、香りが淡く消えていくように不確かで儚いものになってしまったと語ります。この比喩は、人の記憶や人生そのものが、時間という大きな流れの中でいかに形を失い、おぼろげになっていくかという無常観を見事に表現していると言えるでしょう。確かなはずの過去さえ霞んでいく切なさが、静かな筆致で描かれています。
「代助は渝らざる愛を、今の世に口にするものを偽善家の第一位に置いた。」 —— 夏目 漱石『それから』
【解説】
変わらぬ愛と、移ろいゆく心。その間で揺れ動くのが人間なのかもしれません。この一文は、主人公の代助が、多くの出会いと刺激に満ちた都会生活における男女の心理を冷ややかに分析する場面の言葉です。彼は、人の心は環境や新たな出会いによって常に変化し続けるものであり、そのような世の中で「変わらぬ愛」を語ることこそ、自分を偽る行為、すなわち偽善に他ならないと断じます。この理知的な視線は、特に恋愛における感情の「無常」、つまり人の心や関係性がいかに儚く移ろいやすいものであるかを鋭く指摘していると言えるでしょう。物語は、この理屈では割り切れない代助自身の心の行方を追っていきます。
「病気の境涯に処しては、病気を楽しむといふことにならなければ生きて居ても何の面白味もない。」 —— 正岡 子規『病牀六尺』 七月二十六日
【解説】
もし変えられない運命があるとしたら、嘆き続けるか、それとも別の道を探すでしょうか。子規は、自身の過酷な病床生活の中から、驚くべき境地を見出します。それは、単に病苦を諦めて耐えるのではなく、その病気という境涯そのものを「楽しむ」という姿勢でした。避けられない苦痛を嘆いていては、生きていること自体の面白味が失われてしまう。ならば、その状況の中でこそ見出せる心の働きや発見を喜びとし、生を味わい尽くすべきだというのです。これは、人生のはかなさや不条理を正面から受け止めた上で、なおも人間としての尊厳を失わずに生き抜こうとする、子規の壮絶な精神の到達点を示す言葉と言えるでしょう。
「悟りといふ事は如何なる場合にも平気で死ぬる事かと思つて居たのは間違ひで、悟りといふ事は如何なる場合にも平気で生きて居る事であつた。」 —— 正岡 子規『病牀六尺』 六月二日
【解説】
死ぬ覚悟と、生きる覚悟、どちらがより強い精神を必要とするでしょうか。子規は、禅の「悟り」に対する自らの解釈が変化したことを、この対照的な一文で示します。かつては、悟りとはいつでも平気で死ねることだと考えていた。しかし、長く続く病苦の果てに、本当の悟りとは、どんな過酷な状況下でも動じずに「平気で生きて居る」ことなのだと気づいたのです。これは、死へと向かう定めの中で、一日一日を生き抜くことの壮絶さを実感した者のみが到達しうる境地でしょう。人生のはかなさをただ受け入れて消え去るのではなく、そのはかない生を最後まで肯定し続けるという、力強い生命観への転換がここに宣言されています。
「果して病人の眼中に梅の花が咲くであらうか。」 —— 正岡 子規『病牀六尺』 八月二十日
【解説】
もし未来が不確かなら、人は季節の巡りに何を思うでしょうか。この一句は、病床で随筆を書き続けた子規が、百日分の日記を書き終え、残る二百日分の状袋を前にして漏らしたものです。二百日といえば半年以上先、厳しい冬を越えた先に咲く梅の花の季節です。その美しい光景を、果たして自分は見ることができるのだろうか。この静かな問いかけには、死の影を常に意識しながらも、なお来たるべき季節の美しさを想う、詩人の切実な心が込められています。一日を生き延びた安堵の直後に訪れる、自らの命のはかなさへの問いは、読む者の胸に深く突き刺さる無常観の結晶と言えるでしょう。
「人間のいとなみのあとかたもなく消えてしまう果敢なさをあわれみ、過ぎ去った花やかな世をあこがれる」 —— 谷崎 潤一郎『蘆刈』
【解説】
賑わいの声は水面に消え、ただ月の光が古の川面を照らします。語り手が秋の夜、淀川のほとりで月を眺めながら、かつてこの地が遊女や舟で賑わった「天下第一ノ楽地」であったことに思いを馳せる場面の言葉です。過去の文献に記された華やかな繁栄の記憶と、目の前に広がる静まり返った寂しい風景との対比が、強い感傷を呼び起こします。人々が繰り広げた営みが跡形もなく消え去ってしまうことのはかなさを哀れみ、今はもうない華やかな過去の世を慕う気持ちが率直に語られているのです。懐古の情と無常観が溶け合ったこの一文は、歴史の流れの中に立つ個人の、もの悲しくも美しい感慨を見事に描き出しています。
「どうせいつまでながらえられる憂き世の中ではないのだから、歩き倒れて死ぬところまで行ってみよう」 —— 谷崎 潤一郎『三人法師』
【解説】
すべてを失ったとき、人はどこへ向かって歩き出すのでしょうか。主君に裏切られ、すべてを捨てて出家した武士が、修行の旅に出る際の決意を語る一節です。彼は、この世が長く生きられるような場所ではないという諦念を抱いています。その上で、ただ諸国を巡り、行き倒れて死ぬまで歩き続けようという、壮絶な覚悟を固めるのです。人生のはかなさ(憂き世)を達観したからこそ生まれる、一種の開き直りともいえる強い意志が示されています。破滅的でありながらも、そこには自らの運命を己の足で引き受けようとする潔い生き様が感じられ、無常観の先にある人間の強さを思わせます。
(編集協力:井下 遥渚、佐々 桃菜)
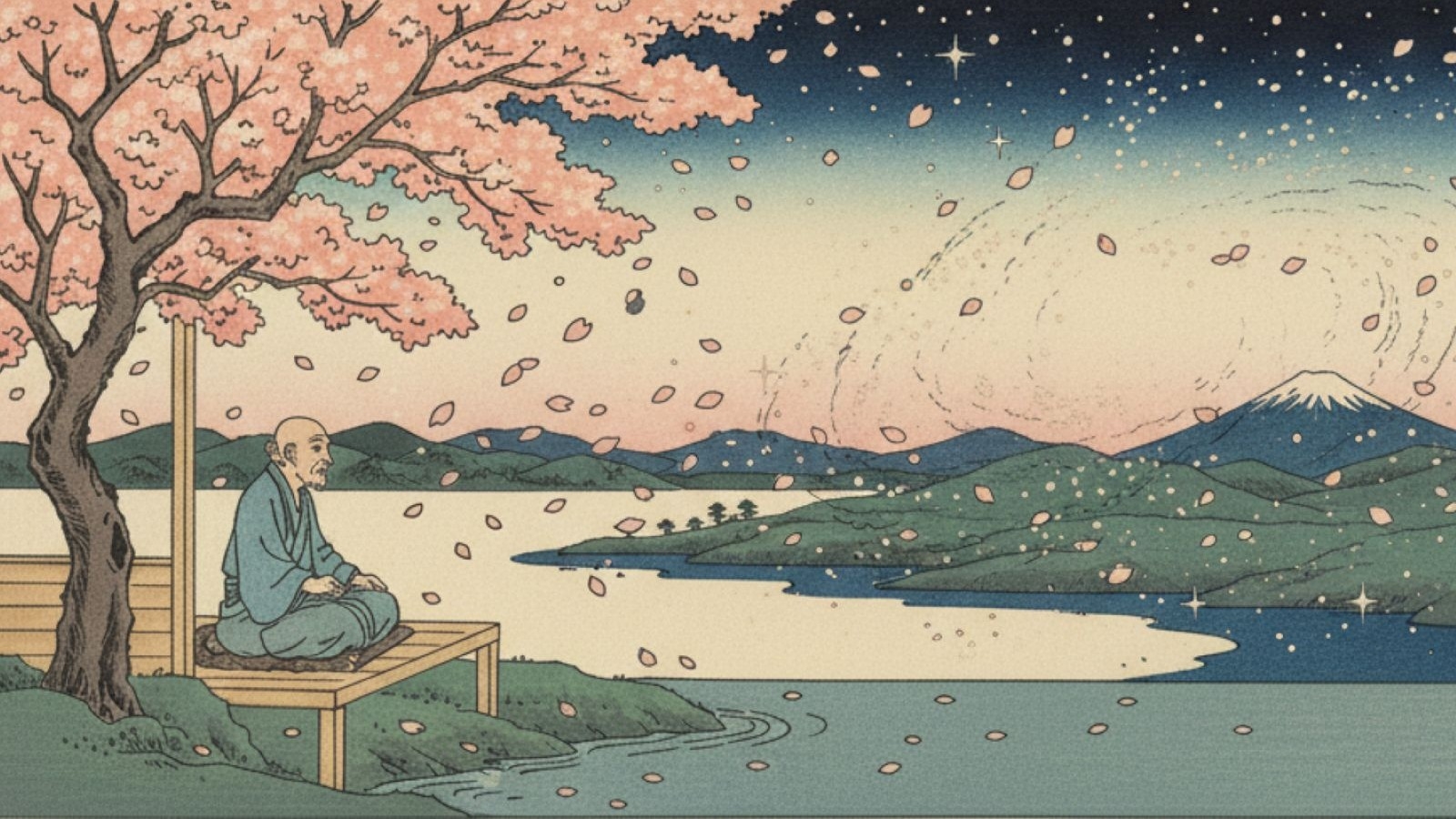
日本の季節観:文人たちのまなざし
日本の文人たちは、小説や随筆などの多様な表現形式を通して、移ろいゆく季節や生命の営みに深く向き合ってきました。彼らの繊細な感性と鋭い観察眼は、私たちに自然との対話の扉を開き、日常の風景の中に隠された美と哲学を教えてくれます。

日本の原風景:土地が語る記憶の物語
ハエの羽音に亡き人を重ね、一本足の案山子(かかし)に神様を見る。 日本人にとって不思議な物語は空想ではなく、すぐ隣にある「生活」そのものでした。 海の彼方への憧れや、古びた塚に残る伝説。柳田國男や小泉八雲らが拾い集めた、恐ろしくも優しい「心の原風景」を旅してみませんか。
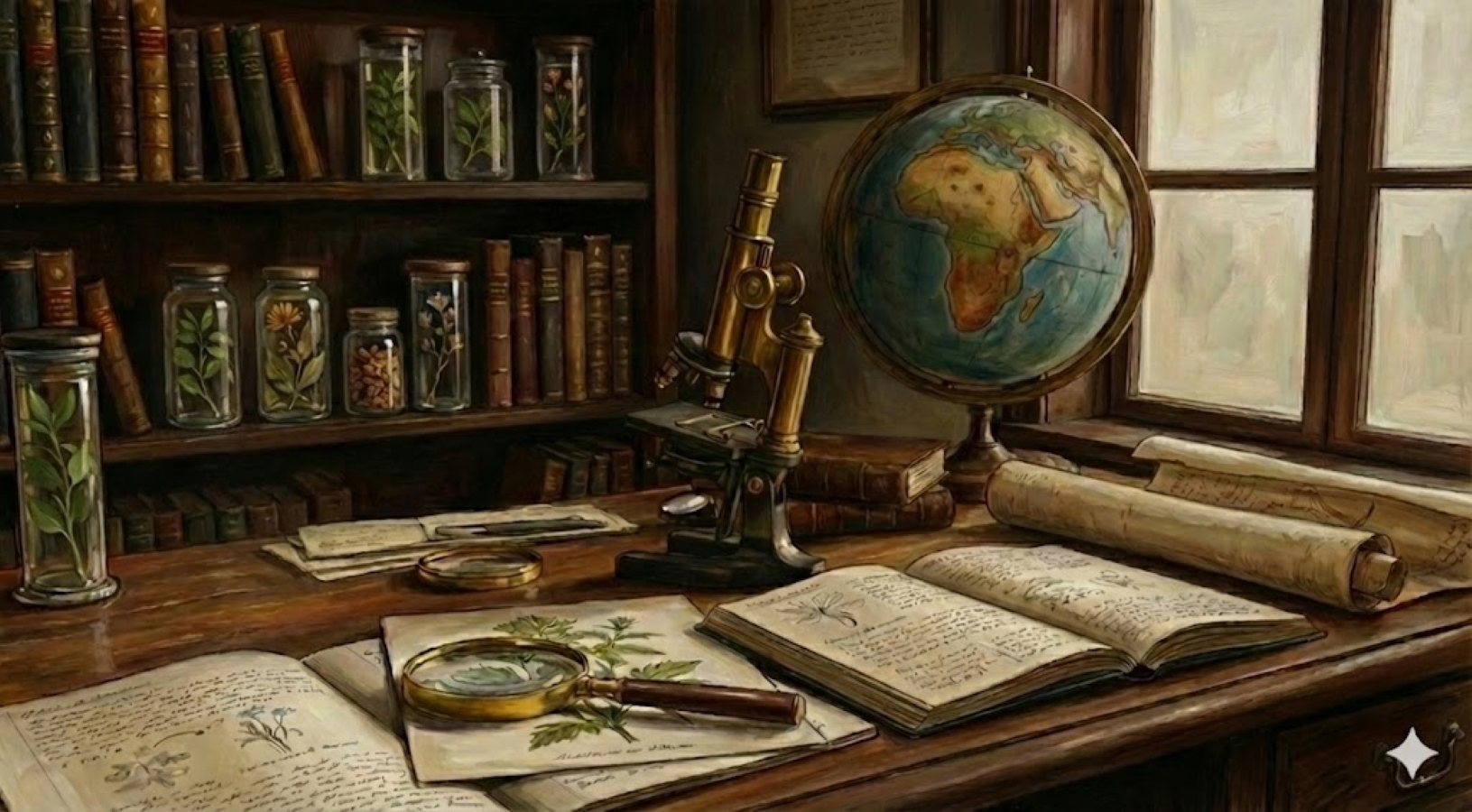
「理屈」を超えた驚異へ:科学者たちが覗いた美しき深淵
科学は、無機質な計算ではありません。それは人知を超えた自然への畏敬であり、終わりのない美の探求です。雪の結晶に宇宙を見、道端の草に命の猛々しさを感じる————。論理の果てにこそ現れる、圧倒的な「神秘」と対峙した知の冒険者たち。その静謐で熱い魂の記録に触れます。

「私」を叫ぶ魂:近代女性が描く、運命と矜持の物語
女性の人生は、運命への諦念で塗り固められるべきでしょうか。それとも、社会の壁を突き破り、自らの「生」を勝ち取るための戦いでしょうか。一葉が吐いた乾いた自嘲、晶子が愛する者のために放った痛烈な叫び。時代という鎖に抗い、泥にまみれながらも「私」を確立しようとした、彼女たちの魂の叫びに耳を澄ませます。
